古物営業の3大義務
古物証許可を取得したからといって、自由に営業ができるわけではありません。
許可を取得した後にも守るべき3つの義務があるのです。
- 古物台帳記帳義務
- 本人確認義務
- 不正品申告義務
古物営業において3大義務を守らなかったり、対応が不適切であった場合には、『許可の取消』や『業務停止命令』が下されたり、『6か月以下の懲役または30万円以下の罰金』、に処せられてしまうケースもあるのです。
しかし、これらの法令対応をすべて自社で完結するのは非常に難しいです。
例えば、以下のようなケースが日々発生するでしょう。
法令対応するための悩み
- 古物台帳をエクセルで管理していたが誤ってデーターを消してしまった
- 本人確認資料をコピーし保存していたが紛失してしまった
- 在庫管理を手作業で行い効率が悪い
- 法令保存期間(3年)分の資料保管のために倉庫を借りている
- 警察の捜査協力において対応が煩雑に
- 法令対応ができず、古物営業法違反となってしまった・・・
- 今まで紙やエクセルで作成していた取引記録をネットで保存することができる為、データー紛失の恐れがありません。
- また、記帳義務がある取引かどうか、さらに本人確認が必要な取引かをシステムが自動判断して教えてくれるので安心です。
- さらに買取り時に在庫を入力することで、営業活動に必要なマーケティング(粗利や原価率、在庫期間など)をシステムが実施してくれるので営業効率が各段にUPします。
古物台帳記帳義務
記帳すべき古物取引をした場合には取引の情報を古物台帳に記帳しなければなりません
さらに、最後に記帳をした日から3年間は保存しておく義務があります。
そして、古物商が古物台帳への記帳義務を守らない場合には、『許可の取消』や『業務停止命令』が下されたり、『6か月以下の懲役または30万円以下の罰金』、に処せられてしまうケースもあるのです
記録すべき内容は古物営業法という法律で決められています。
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴
(4)相手方の住所、氏名、職業、年齢
(5)本人確認の方法
記録すべき内容は想像以上に多く管理も大変です。
そして、古物台帳記録義務に違反をすると、許可の取消しや、古物営業の停止等の行政処分に加え、6か月以下の懲役30万円以下の罰金に処せられるケースもあるのです。
古物営業をする上で絶対に守るべき義務といえます。
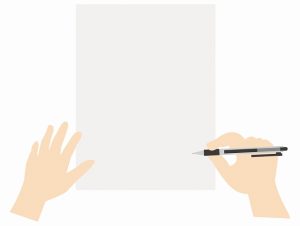
紙で古物台帳に記帳
紙ベースの古物台帳は防犯協会なで2000円程度で販売されています。
ただし、毎回手書きで記帳するのは非常に手間がかかります。
また、紙で保存すると記入の訂正が煩雑であったり、せっかく記帳しても紛失リスクが高いです。
パソコンを使いエクセルデーターで保存する方も増えてます
しかし、パソコンが壊れてしまいエクセルデーターが抽出できなくなってしまったり、
誤ってデータを消してしまったりした場合には修復ができないデメリットがあります。

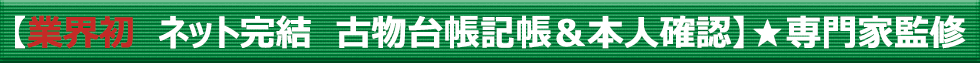
・システム保存なので紛失のリスクがない
・法令に対応した記録ができる
・ボタン1つで古物台帳が出力可能
・記録義務があるかを自動判定
・在庫管理から粗利、利益率まで自動管理
古物商の本人確認義務
古物商は古物を買取りした場合には、相手方の本人確認義務があります。
さらに店舗などでの対面取引とインターネットショップなどでの非対面取引では本人確認の方法も異なり、それぞれ法律に対応した確認が義務付けられます
そして、古物商が古物台帳への記帳義務を守らない場合には、『許可の取消』や『業務停止命令』が下されたり、『6か月以下の懲役または30万円以下の罰金』、に処せられてしまうケースもあるのです
例:店舗での取引やお客様の自宅への出張買取時など
お客様が古物商の店舗に訪れてた場合や、お客様のご自宅へお伺いして出張買取などを行う場合は対面取引となります。
対面取引時の本人確認方法は3つあります
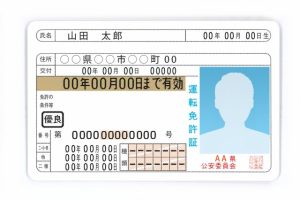
- 運転免許証や健康保険証、顔写真付きマイナンバーカードなどの身分を証明できる資料の提示を受ける。
- 紙や電子機器(タブレット)などを使い、事前に用意した買取り申込書に氏名・住所・年齢・職業などの事項を記載してもらう。
- お客様が未成年者の可能性がある場合には保護者など身元確認できる者に問い合わせを行う
- 非対面時の本人確認 例:ネットショップやアマゾンなどでの古物買取時の本人確認
インターネットショッピングやアプリと古物営業は非常に相性がよく、今後も成長していくビジネスモデルです
ただし、取引の気軽さゆえに、古物商としては本人確認を徹底する必要があります。
理由は対面取引に比べて、非対面取引は『なりすまし取引』に利用されやすいからです。
非対面取引時の本人確認方法は8つあります
- 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること
- 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと(オススメ!)
- 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること
- 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
- 古物商が相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
- 相手方から身分証明書のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと
- 相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける
- 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける
不正品申告義務
古物ビジネスをする中で、必ず出会うのが『盗品や不正品』です。
そして、古物商が盗品や不正品の疑いがある古物を発見した場合には警察に申告する義務が定められてます。
古物許可制度の目的が『盗品の流通防止と被害の早期回復』であることからも必ず守らなければいけない義務の1つです。
日頃から不正取引を未然に防ぐ知識や経験を身につけるとともに、適正な古物取引が保たれるよう捜査には全面協力をしていきましょう。
警察からの差し止めが実施されるケースも
警察は古物商に対し盗品の疑いがある古物に対して『30日以内の期間』を定め古物を保管するよう命じることができます。(差し止め)
差し止めの命令をされた古物商は、この間において古物を売却することができなくなります。
警察の命令に応じない場合には6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので差し止め命令には必ず応じましょう
また、盗品や不正品の疑いがある取引の場合には、古物台帳や本人確認義務が適切に行われているのかも重要な確認ポイントです。
法令対応は確実に行うとともに、万が一の対応ができるように準備しておきましょう。